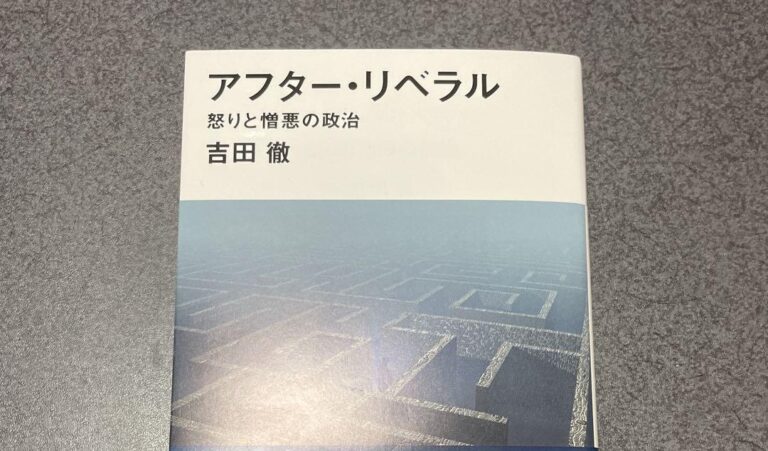本書では、二十世紀後半に政治の原理として支配的になったかに見えたリベラル・デモクラシーが、なぜ危機を迎えているのかを解き明かします。
リベラル・デモクラシーは、リベラリズムの経済的側面の抑制と、民主主義の革命志向の抑制によりリベラリズムと民主主義とが不自然に結合し共存したものでした。
この均衡は次第に失われていきます。政治的対立が階級から離れ、経済的次元ではなく価値的・文化的次元に依拠することになり、これに対抗するものとして権威主義的な政治が出現
してくるからです。
興味深い指摘は、こうした状況を用意したのが68年革命の運動でもあったということです。個人を抑圧する集団や組織からの解放をめざし、個人のアイデンティティの尊重と自己決定権の強化をめざした社会運動は消費社会と新自由主義に親和的なものとなりました。
こうした運動は既存政治をも変え、その政治に対立するものとして権威主義的な政治を招き寄せる結果になってしまいました。
凋落するリベラリズムを再生させるために、著者はいくつかの提案をしています。
ひとつは、個人のアイデンティティそのものを絶対視せず寛容なリベラリズムを対置させることで均衡を取り戻すことです。
もうひとつは、政治が再配分や経済的平等性に敏感になり、社会的平等をもたらす経済的平等のために個人の自由は制約されうるという合意を取り付けることです。
最後に、人々の間の違いではなく、何を共通としているのかについての合意を得る努力を続けることとしています。
本書は、現代という暗い時代の見通しを得ることのできる、大変な労作です。
筆者は一読しただけではまだ飲み込めない部分が大きく、何度も読みたい本だと思っています。